日本銀行の金融政策は、大きく分けて「短期金利の操作」と「長期金利の誘導」という二つの柱で市場金利に影響を与えます。
これが最終的に、私たちの住宅ローンや不動産投資ローンなどの金利に波及していくのです。
1. 短期金利(政策金利)の決定と影響
- 政策金利(無担保コールレート翌日物)の決定:
- 日本銀行は、金融政策決定会合で、金融政策の基本方針を決定します。その中で、無担保コールレート翌日物(金融機関同士がごく短期でお金を貸し借りする際の金利)の誘導目標を定めます。
- 日銀は、この目標金利を達成するために、金融機関から資金を預かる際の金利(当座預金金利)を調整したり、金融機関に対してオペレーション(公開市場操作)を行ったりします。例えば、市場から国債を買い入れることで、金融機関に資金を供給し、金利を下げる効果を狙います。逆に、国債を売却して市場から資金を吸収することで、金利を上げる効果を狙います。
- この無担保コールレート翌日物が、日本の金融市場における最も基本的な短期金利となり、他の短期金利の基準となります。
- 短期プライムレートへの波及:
- 市中の銀行は、自らの資金調達コストや信用リスクなどを考慮して、優良企業向けの最も優遇された貸出金利である短期プライムレートを決定します。
- この短期プライムレートは、無担保コールレート翌日物の変動に大きく影響されます。政策金利が上がれば、銀行の資金調達コストも上がるため、短期プライムレートも上昇する傾向にあります。
- 変動金利型住宅ローンの金利は、この短期プライムレートに連動して決定されることが一般的です。銀行は、短期プライムレートに一定の上乗せ金利(保証料や事務手数料なども含む)を加えて、顧客に提示します。したがって、日銀の政策金利が上がれば、変動金利型の住宅ローン金利も上がる可能性が高まります。
2. 長期金利(10年国債利回り)の決定と影響
- 長期金利の決定:
- 長期金利は、主に10年国債の利回りを指します。国債は、市場で日々取引されており、その需給関係や投資家の将来の金利見通しによって利回りが変動します。
- 日本銀行は、かつては「イールドカーブ・コントロール(YCC)」政策により、10年国債利回りの変動幅を限定的に操作していました。しかし、この政策は2024年7月に撤廃され、現在は市場原理に任せる形になっています。
- イールドカーブ・コントロールの撤廃後は、市場の需給関係や、今後の物価・経済状況、海外の金利動向などによって、より直接的に10年国債利回りが変動するようになっています。
- 固定金利型住宅ローンへの波及:
- 固定金利型住宅ローンの金利は、この10年国債利回りを主要な指標として決定されます。銀行は、国債の調達コストに、事務手数料、リスクプレミアム、利益などを上乗せして、固定金利型住宅ローンの金利を設定します。
- したがって、10年国債利回りが上昇すれば、固定金利型住宅ローンの金利も上昇する傾向にあります。
まとめ:金利決定のフロー
- 日本銀行の金融政策:物価目標の達成のため、金融政策決定会合で政策金利(無担保コールレート翌日物)の誘導目標や、長期金利に対する考え方(以前のYCCのようなもの)を決定します。
- 市場金利への波及:
- 短期金利(無担保コールレート翌日物)の変動が、銀行の資金調達コストに影響し、短期プライムレートを決定します。
- 長期金利(10年国債利回り)は、市場の需給や景気見通し、日銀の金融政策スタンスなどによって変動します。
- 銀行の貸出金利の決定:
- 銀行は、上記の短期プライムレートや10年国債利回りといった市場金利に、リスクプレミアム(貸し倒れリスクなど)、事務手数料、銀行の利益などを上乗せして、最終的な住宅ローンや不動産投資ローンの金利を決定し、顧客に提示します。
- 特に、融資を受ける個人の信用状況(年収、勤続年数、担保評価など)も、銀行が設定する金利に影響を与えることがあります(例:優遇金利の適用)。
このように、金利は、日本銀行の政策を起点とし、金融市場での様々な要素や銀行の個別の判断が複雑に絡み合って決定されているのです。
投稿者プロフィール

-
シニアアドバイザー
兵庫県立大学卒業後、地方銀行に約10年間勤務し法人新規営業等を担当、その後大手生命保険会社を経て保険代理店勤務。
ファイナンシャルプランナーとしてコンサルティング業務を得意とする。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
他の投稿
 不動産M&A2025年9月12日事業承継からポートフォリオ再編まで。不動産M&Aの活用事例とメリット
不動産M&A2025年9月12日事業承継からポートフォリオ再編まで。不動産M&Aの活用事例とメリット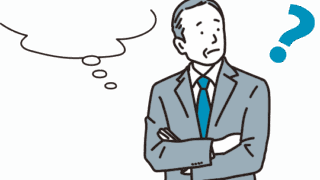 不動産M&A2025年7月25日【金利ってなに?】日本銀行の政策金利と市場金利の決定メカニズム
不動産M&A2025年7月25日【金利ってなに?】日本銀行の政策金利と市場金利の決定メカニズム 不動産M&A2025年7月3日SPCを活用した不動産M&Aスキームとは?
不動産M&A2025年7月3日SPCを活用した不動産M&Aスキームとは? 不動産M&A2025年6月26日不動産M&Aの隠れた課題:非協力的な株主問題とその解決策
不動産M&A2025年6月26日不動産M&Aの隠れた課題:非協力的な株主問題とその解決策



