法定耐用年数とは、税法で定められた「減価償却」を行うための年数のことです。これは建物の構造によって異なり、建物の実際の寿命とは必ずしも一致しません。
以下に、主な建物の構造ごとの法定耐用年数を示します。
| 構造 | 法定耐用年数 |
| 木造・合成樹脂造 | 22年 |
| 木骨モルタル造 | 20年 |
| 鉄骨造(骨格材の厚さ3mm以下) | 19年 |
| 鉄骨造(骨格材の厚さ3mm超4mm以下) | 27年 |
| 鉄骨造(骨格材の厚さ4mm超) | 34年 |
| レンガ造・石造・ブロック造 | 38年 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | 47年 |
| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 47年 |
【注意点】
- 上記は一般的な住宅・事務所などの耐用年数です。工場や倉庫など、用途によって異なる場合があります。
- 法定耐用年数はあくまで「税務上のルール」であり、建物の実際の寿命を示すものではありません。適切なメンテナンスを行えば、法定耐用年数を超えて使用することは可能です。
法定耐用年数と融資の関係性
金融機関が不動産への融資を検討する際、法定耐用年数は融資の可否や期間を決定する上で重要な判断材料となります。その関係性は主に以下の通りです。
1. 融資期間の基準になる
多くの金融機関は、「法定耐用年数 - 築年数」 を融資期間の上限とする傾向があります。
- 例1: 新築RC造マンションの場合 法定耐用年数47年 - 築年数0年 = 残存耐用年数47年 → 最長で30年~40年程度の融資期間が期待できる可能性があります。
- 例2: 築25年のRC造マンションの場合 法定耐用年数47年 - 築年数25年 = 残存耐用年数22年 → 融資期間は最長で22年程度に設定されることが多いです。
このため、築年数が古い物件ほど、融資期間が短くなり、毎月の返済額が増えるため、キャッシュフローが厳しくなる可能性があります。
2. 融資の可否に影響する
一般的に、法定耐用年数が残っている物件は融資を受けやすいですが、耐用年数を超えた物件は融資のハードルが高くなります。
ただし、これは一概には言えません。金融機関は、物件の価値を以下の観点からも総合的に判断します。
- 収益性: 高い家賃収入や安定した入居率が見込めるか。
- 担保価値: 土地の評価額が高いか。
- 買主の属性: 買主の信用力や資産背景はどうか。
- 物件の状態: 築年数が古くても、大規模修繕が行われ、物件の状態が良いか。
そのため、法定耐用年数を超えていても、高い収益性や良い状態の物件であれば、融資を受けられる可能性は十分にあります。
3. 減価償却費を通じたキャッシュフローへの影響
法定耐用年数は「減価償却費」の計算に用いられます。減価償却費は帳簿上の費用であり、実際の現金の流出を伴いません。
減価償却費の計算式 減価償却費 = 取得価額 × 償却率
- 中古物件の減価償却期間 中古物件の場合、法定耐用年数を基に減価償却期間を計算します。築年数が古いほど減価償却期間が短くなり、1年あたりの減価償却費が大きくなります。
- 融資との関係性 減価償却費は、会計上は「赤字」と見なされることがありますが、実際のキャッシュフローは手元に残ります。金融機関は、融資の返済能力を判断する際に、この「利益+減価償却費」を重視します。減価償却費が多い物件は、税引前利益が圧縮されるため、節税効果が高まります。
まとめ
不動産M&Aにおいては、単に物件の価格や利回りだけでなく、法定耐用年数と融資の密接な関係を理解することが不可欠です。築古物件を検討する際は、残存耐用年数、融資期間、キャッシュフローを総合的に分析することが成功のカギとなります。
投稿者プロフィール

-
執行役員 COO
関西大学卒業後、大手不動産仲介会社にて不動産仲介業務を経験、その後一般事業法人の不動産部門にて収益物件の購入、開発、管理等を担当。
また不動産ファンドでのファンド運営にかかわり、ゲームソフト会社の関連不動産会社の代表を経験。自身でも不動産管理会社、不動産仲介会社を経営するなど不動産に関する業務全般に精通。
宅地建物取引士 / 公認不動産コンサルティングマスター / 関西大学不動産会副幹事長
他の投稿
 不動産M&A2025年10月10日法人で不動産購入を検討の際は、出口戦略に不動産M&Aを見据えて!
不動産M&A2025年10月10日法人で不動産購入を検討の際は、出口戦略に不動産M&Aを見据えて!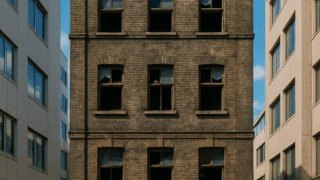 不動産M&A2025年8月4日建物の法定耐用年数一覧
不動産M&A2025年8月4日建物の法定耐用年数一覧 不動産M&A2025年7月14日【不動産投資の真実】なぜ「良い立地」の不動産は市場に出回らないのか?
不動産M&A2025年7月14日【不動産投資の真実】なぜ「良い立地」の不動産は市場に出回らないのか? 不動産M&A2025年7月2日法人所有不動産の売却:「清算」か「M&A」か?税金面から徹底比較
不動産M&A2025年7月2日法人所有不動産の売却:「清算」か「M&A」か?税金面から徹底比較



