はじめに
企業の事業承継や再編の手段として注目される不動産M&A。特に、不動産の取得を主目的として会社ごと買収する「株式譲渡」スキームは、登録免許税や不動産取得税がかからないという税制上の大きなメリットがあります。
しかし、この株式譲渡型の不動産M&Aには、「含み益」という魅力的な要素の裏に、「将来的な税金負債」という見えにくいコストが潜んでいます。この潜在的なコストを理解せずM&Aを進めると、買収後に大きな負担を背負うことになるため、その仕組みを理解しておくことが極めて重要です。
1.資産の価値と「含み益」の正体
企業が保有する不動産は、取得時からの値上がりや長年の減価償却によって、会計上の「帳簿価額(簿価)」と、現在の市場価値である「時価」に大きな乖離が生じていることがよくあります。
この「時価が簿価を上回る差額」こそが「含み益」です。
含み益は、その不動産が持つ本来の経済価値を示すものであり、一見すると買収対象企業の魅力度を高めるプラス要素のように見えます。
含み益 = 不動産の時価 - 不動産の簿価
2.買い手が引き継ぐ「将来的な税金負債」
株式譲渡によるM&Aでは、不動産そのものではなく「不動産を保有する会社の株式」が売買されます。このとき、会社の保有する不動産の簿価はそのまま引き継がれます。
これが、「将来的な税金負債」が発生する理由です。
買い手が会社を引き継いだ後、もしその低く設定された簿価の不動産を時価で売却した場合、含み益の全額が「売却益」として顕在化し、これに対し法人税等の実効税率(約30%〜)が課税されます。
つまり、買い手は不動産という資産価値と同時に、その含み益に対する「将来の税金支払い義務」という負債を潜在的に引き継いでいることになるのです。
3.企業価値評価(バリュエーション)への反映
M&Aの最終的な買収価格を決定する際、この将来的な税金負債は必ず調整されなければなりません。
買い手からすれば、将来的に支払うことになる税金分を、現在の買収価格から差し引いて評価するのが合理的です。
実務上は、以下のように含み益から将来の税金負担額を算出し、これを純資産から控除します。
将来的な税金負債 = 含み益 × 実効税率
買収価格は、この「将来的な税金負債」を適切に考慮した上で設定されるべきです。
まとめ
不動産M&Aは、税制面でメリットの多い魅力的な手法ですが、「簿外債務」だけでなく、この「将来的な税金負債」という隠れたコストを正確に評価することが成否を分けます。
買い手はデューデリジェンス(詳細調査)を通じて、不動産の時価と簿価を厳密に比較し、将来の税負担を見積もる必要があります。この複雑な評価と交渉を成功させるために、不動産M&Aの専門家である当社にぜひご相談ください。
投稿者プロフィール

-
アドバイザー
神戸学院大学卒業後、大手不動産会社で東京勤務、不動産仲介業務にあたる。
その後、実家の不動産会社で勤務した後に独立、不動産仲介業務を行う。
宅地建物取引士 / 管理業務主任者 / 行政書士
他の投稿
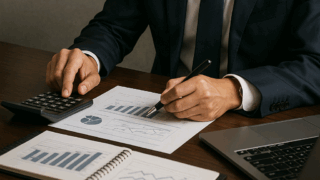 不動産M&A2025年10月27日不動産M&Aの隠れたコスト:含み益と「将来の税金負債」を見落とすな
不動産M&A2025年10月27日不動産M&Aの隠れたコスト:含み益と「将来の税金負債」を見落とすな 不動産M&A2025年10月13日大阪の不動産M&Aを徹底サポート!専門家集団が導く事業承継と資産の未来
不動産M&A2025年10月13日大阪の不動産M&Aを徹底サポート!専門家集団が導く事業承継と資産の未来 不動産M&A2025年10月6日高市新総裁が不動産業界にもたらす「サナエノミクス」の行方
不動産M&A2025年10月6日高市新総裁が不動産業界にもたらす「サナエノミクス」の行方 不動産M&A2025年9月22日北海道の地価高騰から読み解く、日本の不動産トレンド
不動産M&A2025年9月22日北海道の地価高騰から読み解く、日本の不動産トレンド



